JA助けあい組織
1.取り組み経過
JA助けあい組織活動については、昭和60年(1985年)の「農協生活活動基本方針」の中で、「JA助けあい組織(農協婦人部や年金友の会等)が有償ボランティア活動を展開し、一人暮らし・寝たきり高齢者を援助するための在宅福祉活動を展開する」ことをJA大会で決議し、組織的な展開が始まりました。
その後の大会でも、高齢者対策活動の重要な組織と位置付けられ、特に介護保険制度がスタートした平成12年には、介護が必要となった高齢者への福祉活動・事業としては、「助けあい活動」と「JA介護保険事業」を車の両輪と位置づけ、厚生連の支援を受けつつ推進していくことを決議しました。
平成24年第26回JA全国大会においては、『豊かで暮らしやすい地域社会の実現』を柱として、『住み慣れた地域での「助けあい」を軸とした地域セーフティーネットの構築』を決議し、『「健康寿命100歳プロジェクト」の取組み』の中で、「組合員・地域住民によるJA助けあい活動の展開」として、インフォーマルサービスの提供主体として、助けあい組織を位置づけました。
2.現状と課題
JA助けあい組織設置JA数・組織数等は、表1のとおりです。
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| JA数 | 584 | 562 | 551 | 537 | 507 |
| 組織設置JA数 | 207 | 196 | 202 | 200 | 191 |
| 助けあい組織数 | 465 | 484 | 488 | 482 | 488 |
| 協力会員数(人) | 24,969 | 23,682 | 24,499 | 21,108 | 18,305 |
JA助けあい組織の主たる活動メニューとしては、ミニデイサービス、施設(病院・特別養護老人ホーム等)におけるボランティア、元気高齢者健康教室、声かけによる安否確認など、高齢者への生活支援サービスから生きがい活動、学習活動などさまざまな分野に及んでいます。
これまで新型コロナウィルス感染症の影響により、「活動は縮小」あるいは「活動実態なし」と回答のあった組織が約半数という状況だったが、「順調に拡大」、「現状維持」が7割を超えるまで回復してきています。(表2参照)
-
活動の現況 組織数 割 合 ・順調に拡大 42組織 9.3% ・現状維持 290組織 63.9% ・活動は縮小 80組織 17.6% ・活動実態なし 42組織 9.3%
JA助けあい組織は、当初はその多くがJA女性組織の中の専門部会として設置され、発展を遂げてきましたが、令和6年度調査では、JA女性組織の活動の一環として活動している組織は全体の45.0%、JA女性組織とは別の組織として活動している組織は55.0%となっており、別組織化が続くものと推定されます。
また、設立当初の目的は高齢者福祉活動を中心とする方針が掲げられスタートを切りましたが、平成17年「JA助けあい組織のあり方(今後の方向性)」(全中取りまとめ)では、これまでの経過を踏まえながらも、「活動の趣旨と基本方針をJAが掲げるJAの一組織と位置づけ、JA高齢者福祉活動も含めた協同組合運動を地域住民へ広める住民参加型の組織」との考え方を示しています。
つまり高齢者に限らず「誰もが、住み慣れた地域で安心して生活する環境を得たい。」という願いを実現するため、組合員や地域の人々がお互いに助けあう意思を持ち、自主的・自発的に集まりJAの協同組合活動を通じて実践する会員制組織が、JA助けあい組織といえます。
JA助けあい組織のマークについて
ハーモニー(調和)の頭文字「H」を図案化し、介護する側と受ける側の心のバランス、調和を人間の形でデザインしたもの。
常に支え合う、そして心を通わせる日々をイメージしています。
また、地域の人々がJA助けあい活動に参加して、互いに学びあい助けあって、
これからの高齢社会を笑顔で迎えることができるようにしようという願いをこめています。


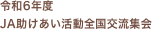

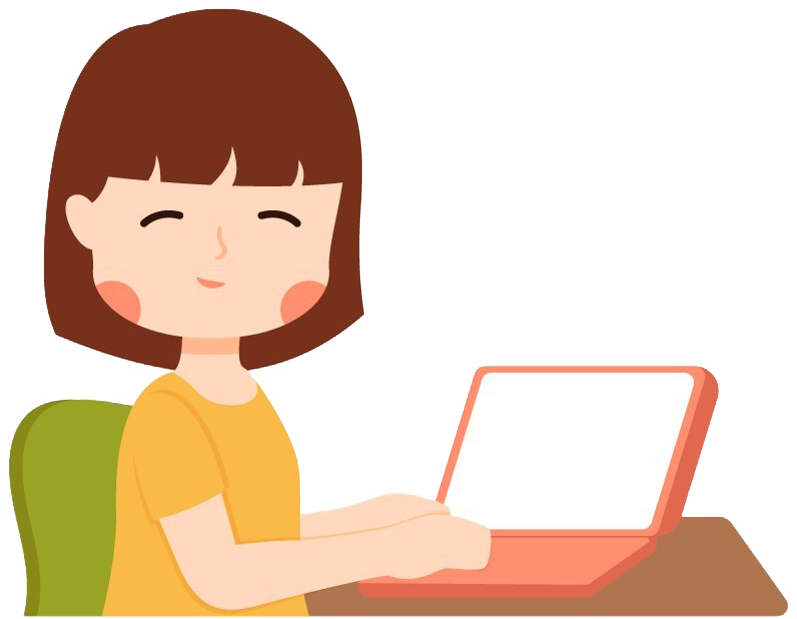 研修会
研修会